あなたは、無意識のうちに空気を飲み込んでいませんか?
日本人の内、8人に1人は空気を飲み込んでしまう『空気呑氣症』になっているそうです。
☆:呑氣症(どんきしょう)別名:空気嚥下症(くうきえんげしょう)
呑氣症は、別名で空気嚥下症と呼ばれています。
『嚥下』とは、モノを飲み込む胃に送ることを表す言葉です。
知らないうちに大量の空気を飲み込んでしまうことで、さまざまは症状が現れる病気を、
呑氣症(空気嚥下症)と呼びます。
人は、食事や飲み物を取る時に、一緒に空気も飲み込んでいます。
呑氣症の人は、その量が多かったり、食事以外にも日頃から無意識に空気を飲み込みが多い傾向があります。
呑氣症の症状は、大量の空気を飲み込むことにより、胃や食道、腸に空気が溜まる事で起きます。
その結果、このような症状が出ることがあります。
・ゲップが頻繁に出る
・臭くないおならが出る
・腹部膨張感
・腹痛
・胸焼け
・吐き気
このような症状にくわえ、歯をかみしてしまうことで起きる『噛み締め呑氣症候群』という症状が出る事があります。
これは、無意識に歯を噛み締めている事が原因です。
顎の痛みやだるさ、頭痛や肩こりや痛み、歯の磨耗やひび割れ、ふらつきなどが起こります。
呑氣症の原因は、大きく分けて2つの原因が潜んでします。
私達は、口をあけて食べて物・飲み物を摂る時に、飲食物や唾液と一緒に空気も飲み込んでいます。
呑氣症の場合は、意識せずとも日常生活の中で空気を、たくさん飲み込んでしまっている傾向があるようです。
2つの要因が考えられます。
◎身体的な要因、他の基礎疾患
・口呼吸
口呼吸は、口を乾燥させ唾液の分泌量を増やします。その結果、空気を飲み込む回数が増えてしまい、呑氣症のリスクが高くなってしまいます。
特に、鼻づまりやアレルギー性鼻炎の人は、こっちの症状を軽くする工夫も必要になります。
普段から、鼻呼吸を意識するようにするとスムーズに出来るようになります。
・姿勢が悪い
猫背などの姿勢が悪いと、内臓機能が乱れやすくなり、前屈みは余分な空気を吸いやすくなります。
・食べ過ぎ
一気にたくさんの食事を摂ることで、胃腸に負担をかけて消化不良を起こしやすくなります。
その結果、お腹にガスが溜まりやすくなり、呑氣症の原因になることがあります。
◎他の基礎疾患
・逆流性食道炎
頻繁なゲップにより胃液や食べた物が逆流することで、胸焼けを感じ逆流性食道炎になることがあります。
原因は、胃酸の出すぎによるものです。この逆流性食道炎の症状と呑氣症の症状が似ており併発させる可能性があります。
・非びらん性胃食道逆流症
食道下部の粘膜に炎症がないのに、胃液が逆流し、胸焼けや胃痛、のどの痛みなどの症状が表れます。
逆流性食道炎と症状は似ています。
・過敏性腸症候群
ストレスを感じる場面が近づくと、下痢や便秘になったり、胃腸の不具合を感じることがあります。
この過敏性腸症候群と呼ばれる病気は、腹部が腫れ上がったり、おならとして空気やガスが頻繁に出ることがあります。
呑氣症を併発する可能性があります。
・噛みしめ呑氣症候群
歯を噛みしめる事で、下が上の顎につき唾液が奥へと流れやすくなる為に、自然と唾液を飲み込む回数が増えていき、
それと共に、空気を吸い込む回数も増加してしまいます。
ゲップや腹部膨満感にくわえ、頭痛・肩こり、眼の痛み、ふらきつなどの噛みしめ呑氣症候群という症状が出やすくなります。
症状によりけいですが、
・ゲップやおならなどの呑氣症の典型的な症状がみられる場合は、まず内科や消化器科
・歯や顎の痛み、頭痛などの症状は、歯科や口腔外科
・不安感やストレスを感じやすく、呑氣症の症状が長く続く場合は、心療内科や精神科
を受診されるといいかと思います。
呑氣症ではなく、逆流性食道炎などの基礎疾患を抱えている場合は、まずはかかっている病気を治すことに専念してください。
☆:自分で出来るケアとして
・ストレスを溜めない
・悲観的にならない
・早食いの人は、ゆっくり噛んで食べる習慣
・食物繊維を取り過ぎないように氣をつける。(目安は1日20mg)
(便秘気味の人が食物繊維を取りすぎると、腸内の水分を吸収しすぎてしまう為注意が必要です。)
・姿勢を氣をつける(猫背やスマホを見る時など)
・ガスを発生させる食事に注意(ゲップがうまく出ないや苦しい時はなどは、少し飲んでゲップを楽に出す手伝いもするようです)
・食べ物と身体を観察(脂っこい食事や辛い食事は控えましょう)
・ガムを噛まない(ガムを噛むと空気まで飲み込んでしまう為です)
・喫煙はやめましょう。
などがあります。
あと、ツボを押すのもひとつの手かと思います。
ツボには、自律神経の乱れに効くツボ、胃腸の効くツボなどありますので、
そういったツボを刺激するのも言いかと思います。
お腹は全身の中でもやわらかくデリケートな部位です。
押す(指圧)する際は、力を入れすぎないように注意してください。
ゆっくり息を吐きながら、ツボを押すとより効果的です。
・天枢(てんすう)

おへその付近に2ヶ所あるあるツボ。おへそから指2~3本分外側に離れた部分にあります。
人差し指、中指、薬指の3本の指をそろえて、左右のツボを同時に押しましょう。
お腹が軽くへこむぐらいの強さで力を入れれば十分です。
・大巨(だいこ)

おへそのそばに左右2か所あるツボです。おへそから指2~3本分外側に離れ、
さらに指2~3本分下がった部分(つまり、天枢から指2~3本下がった場所)が大巨です。
この大巨は下腹部膨満感や尿量や回数が少ない、動悸、不眠などにも効果があります。
2か所ありますが、こちらはまとめて押さずに1か所ずつ順番に押しても大丈夫です。
硬くなっている場合はついつい強く押してしまいがちですが、押しすぎは禁物です。
その際は、両手の人差し指と中指を重ねてゆっくり押し揉むようにします。
・ちゅうかん

ちゅうかんは、おへそとみぞおちを結ぶ縦線の、ちょうど中間のあたりに位置するツボ
両手の指を揃え、正面からまっすぐに刺激します。
・氣海(きかい)

氣海は、下腹部に位置するツボで、おへそから指2本分下に下がった部分
正面からまっすぐに両手の指で押します。
また、ちゅうかんと氣海は一直線上にありますので、握り拳で軽く押しながらこするように上下させると、
双方のツボに適度な刺激を与えることが可能です。
これらのツボへの刺激とともに『の』の字マッサージなどの便秘マッサージを組み合わせることで、
腸への刺激はより大きなものとなります。
ご自身でマッサージや指圧(ツボ押し)などをする際の注意点
1.マッサージや指圧などは身体に影響を及ぼす行為です。
ご自身・ご家庭で行う場合は、部位の把握や力の加減が難しく、身体への影響には個人差があります。
2.病気やケガ、痛みがある場合は、マッサージや指圧などをするまえに医師の診断やアドバイスを受けましょう。
3.食後、飲酒時、妊娠中など、普段と異なる体調の際は、自己判断によるマッサージや指圧などは避けましょう。
4.マッサージや指圧などをしたことで体調が悪くなったり、痛みなどが出た場合は、
すぐに医師に相談しましょう。また、症状が改善しなかったり悪化したりするようなら、医療機関を受診しましょう。



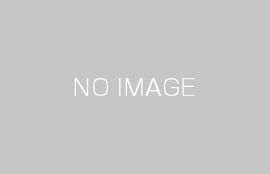
背景透明.png?1751738435)